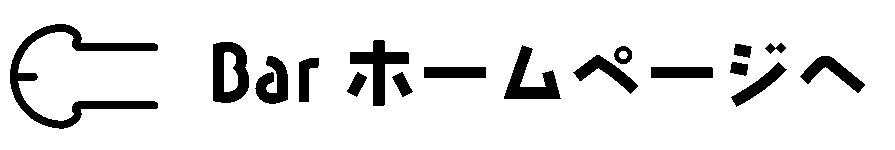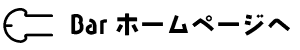『バーチャルボーイ』
ありまけんすけ君の家はとてもお金持ちで、ゲームがハードもソフトも何でも揃っていた。
だからゲームの最新作が出たときはみんなでありま君の家に行くのだけれど、それは同時に大きな冒険を伴うものだった。
「ありまん家にマリオサンシャインやりに行く人~?」
帰りの会の後、馬場君が5年2組全域に向けて声かけした。俺はすぐに足を踊らせながら「ハイハイハイ!」と猛烈な挙手で意思表示をした。
俺はこの声かけに応じることを昨日の夜寝入りながら予習していた。ありま君とは普段からよく遊ぶグループではなかったし、外様の人間は声がかかるまで沈黙するのが慎ましい態度というものだ。
メンバーはありま君に馬場君、木下君という仲良し三人組に加えて俺、佐藤という5人編成となった。ありま君の家に行ったことがないのは俺だけだったが、佐藤とは1年生の時からクラスが一緒で家も近い。お調子者な性格で誰とでも仲良く接することができるので、俺は佐藤の存在があるこの編成に安心感を覚えていた。
ありま君ちへ続く、閑静で、それでいて心なしかそれぞれの敷地同士がゆったりとしている住宅街の坂道を歩いている最中、佐藤が聞いた
「ありま、今日は家誰いんの?」
「兄貴だけ」
「お、じゃあ、チャンス多いかんじ?」
ありま君には歳の離れたお兄さんがいる。実は家のゲームのほとんどがそのお兄さんの所有下にあって、特に最新ソフトともなれば、ありま兄の部屋に誰かが忍び込んで“仕入れて”くる必要があった。でも問題なのは、そのお兄さんがほとんど部屋から出てこないことだった。家の跡を継ぐから、医学部に行くための勉強をありま君が2歳の頃から続けているらしい、みたいなことを誰かから聞いた。
そして一番問題なのは、弟のありま君が頑なに自分では取りに行きたがらないことである。余程嫌な思い出があるのか、自ら兄の部屋へ入ることは決してなく、やりたいゲームがあるときは必ず誰かを家に招いて兄の部屋へけしかけさせていた。貧乏な家が多いこの辺の子供は、こんな需要と供給を甘んじて受け入れていたのだ。
家に着くと、「早く!」とありま君に急かされ、全員でダバダバと玄関前のやたら白い階段を駆け上がった。床が暖かい、テレビが大きい、良い匂いがする。お金持ちの家の圧倒的な説得力を、駆ける視界の中で避けられもせず感じた。途中、階段を上がって直ぐ左側の部屋を視界の片隅に捉えた。お兄さんの部屋だ、と直感で判った。そこだけ人の世が携わっていないような、異界への扉に思えた。俺はそこで初めてほんの少し、怖くなった。
ありま君の部屋は、その1つ隣にあった。漫画や少し前のゲーム機などが雑に纏められている。しきたりなのか、まずみんなでジャンケンをして、負けた木下君と佐藤がキッチンに菓子とジュースを取りに行った。ありま君はちょっと見てこいといった風に、嫌そうな馬場君をありま兄の部屋の前まで偵察に行かせた。
「あ、ありま君の兄ちゃん、マリオサンシャインまじでもうやってないの」残ってしまった俺はありま君にひそりと話しかけた。
「もう全クリしたんじゃない、格ゲーしてる音聞こえるし」
「え、じゃあ頼んじゃダメなの?貸してくださいって」
「は??そんなことできる訳ねえだろ、バカ!!お前じゃあいえんのかよ、ウチにきたの初めてのくせに勝手なこと言ってんじゃねえよ」
俺は「ごめん」と言い、勝手なことをしないように体育座りで小さくなった。
ありま兄の部屋への仕入れ部隊の選出は、スマブラで決めることになっていた。俺は久しぶりにスマブラができるだけで嬉しくって仕方がなく、別に今日はこれだけでも良いな、なんて思っていた。しかしゲームが始まると、他の三人は一斉に俺のマリオに集中攻撃を始めた。あっ、最初から俺は兄貴の部屋に行かせるための生贄だったんだ。一気に黒い気持ちが頭からコントローラーを持つ手まで覆っていく。何より佐藤にも裏切られたことがショックだった。俺は操作する気力がなくなり、ふと隣の三人の顔を覗き込むと、様子は思っていたものと違っていた。その顔は人を貶めようとかそれを楽しんでいる人間の顔ではない。必死に命を繋ぎ止めようとする者の顔をしていた。スマブラは俺の最下位で決着が着いた。
「ありまん兄ちゃんが部屋から出て、階段下り終えたらGOな!」
木下君は急に親しげになり、実行時のポイントを俺に説明した。
「ていうか勝手にとってバレたらどうすんの?」
俺は完全に怖気づき、実行しない言い訳を見苦しく喚いた。
「兄貴は自分の部屋以外では人と絡まんから平気だよ」
兄のよく分からない生態ルールを理由として掲げるありま君は、続けて得意げに言った「部屋から出れば、こっちのもん」
「大丈夫、俺らもみんなやってっから」
他の三人の眼差しと言葉は、とても暖かく感じた。きっと、これはここでゲームを遊ぶための禊のようなものなんだろうな、ゲームを調達して来ることで俺は仲間として暖かく迎えられるんだろう、そう思うと勇気が湧いた。
「ゲームキューブとコントローラーも忘れんなよ!」ありま君が忠告してきた。
大きなものが動いた。
しっかりとした作りの建物なのに、確かに全体が軋むような音を立てている気がする。ドアの開く音。全員が息を殺した。階段を降る音は、空間を蹂躙するように、姿を見ていないのにそれが巨体だとはっきりと分かる。
「いけ!!!!」馬場君が顔だけでそう言った。
俺は爪先立ちのまま自らの出せる最高のスピードで目的地へ駆けた。
ドアを開けると、異臭が熱気とともに顔を覆った。近所のホームレスの臭いとも牛乳で汚して数日放置したランチョンマットとも異なる、新体験の臭気だった。部屋は薄暗く、ゲームを映すTVモニターの灯りが部屋の片隅を照らしている。モニターへ続く細い動線以外は夥しい数の物が積み重なっており、クレパスの底にいるような気持ちになった。俺はまず電気をつけるかこのまま探すかの二択を実行出来ないまま、場に呑まれてしまった。ただ、足元から散乱している“物”を次々と手に取り、見ていった。何も考えてはいなかった。
大きなものが下から上へと、急速に近づく音がした。隣から微かに、「やべえ」「閉めろ」などの声もした気がする。
俺は壁際に取手を見つけると、その前に積まれていたものを崩し倒し、咄嗟にその中に入った。直後、ドアが勢いよく開き、怪獣のような地響きがした。
ずしり ばさ がしん ずし ずし
おそらくは─クローゼットの中からじっと息を殺した。そこはクローゼットとしての機能が物置としての機能に侵食されており、上から下がっている衣服類よりも、雑に入れ込まれた得体の知れない箱やら硬い物やらが狭い空間に敷き詰められていた。俺は足場を確保することができず、何かしらの硬い物の角に腹や足をめり込ませながら音を出さない様に耐えていた。
この生物がゲームを始めたら直ぐ逃げよう、そんな算段をしていた矢先に、呆気なくクローゼットのドアは開けられた。
濡れている、と思った。
その生き物は髪が濡れたように脂で光っていて、興奮した獣のような大きな鼻息が音を立てていた。相貌は黒目しかない細い目に、今にもポロポロとこそげ落ちそうな角質が顔を覆っている。
「こんにちは、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい」俺は必死に謝りながら体を小さく丸めることしかできなかった。
「何盗った??お前っ、ふざけんな潰れるだろ!チッ! チッ! チッ! チッ!」
俺は腕を掴まれ、クローゼットの外へ引き摺り出された。熱い体温と吸い付くような手汗を感じた。
男は物凄い速さで舌打ちをしながら、元からグチャグチャだったガラクタを整理している。思えばこれが最後の逃げるチャンスだったのかもしれない。
「何盗った????」
「何、何も盗ってないです」
「チッ!何を盗りにきたかって聞いてんだよ、あいつに仕向けられてんだろ、全部わかってんだよこっちはよ」
「スーパーマリオサンシャインです」
「フガッ」鼻の音を鳴らされる。笑ったのか怒ったのか分からない返事だった。
そのとき、数人が階段を一気に駆け下りる音が聞こえた。
「おい、お前の友達全員逃げたぞ」男は全く白い部分のない歯を見せて笑った。
隣に仲間がいる、それだけがこの場で正気を保っていられる生命線だった。宙ぶらりんだった恐怖が一気に押し寄せてきた。
「あいつ、クズだろ?昔っから人のもんだけ盗って生きてるからな、あいつ、マジでゴキブリだな。連れてこられたお前もゴキブリか?お前はなんだ?ゲーム好き?」
「あの、好きだけど、家に全然ゲームなくて、それで、ごめんなさい」
「お前もゴキブリゲーマーじゃねえか。人の物で遊びたい時はちゃんと貸してください、って頼む常識知らないの?」
「…ごめんなさい」
俺はそう提案したがあなたの弟が却下しました、と主張したかったが、俺は怒っている大人に口を挟むことは全て“言い訳”として捉えられる事がわかっていたのでただ謝意を表した。
「ちゃんと頼めよ」
「わかりました、すいませんでした」
「そうじゃねえだろ、「ゲームを貸してください」だろ」
「ゲームを貸してください」
もうゲームなんてどうでも良かったが、いう通りにした
「いいよ、コレで俺に勝ったら貸してやるよ」
ありま兄はクローゼットの中から、カメラの三脚めいたものが生えた、赤くて大きいゴーグルのようなものを取り出した。

「何?ですか」
「バーチャルボーイ」
何でもこれはゲーム機で、ゴーグルの中を覗き込むと映像が飛び出して見えるらしい。俺がこれを知らなかったことは、ありま兄のさらなる失望と怒りを引き出した。
「普通喜ぶからな、ゲーム好きは。バーチャルボーイだぞ」
喜べないのは知らなかったからだけではない。コントローラーには食べカスや手垢が、油膜のようなものでこびりつき、疫病に罹った肌を思わせた。ゴーグルの顔との接着部周辺は、異様な光沢を帯びており、皮膚の欠片や毛穴の角栓とおぼしき黄褐色の粒が散らされていた。
「マリオ好きなんだろ?ゲーム、マリオクラッシュにしてやるよ」そう言ってありま兄は本体の電源を付けると、バーチャルボーイのゴーグルへ顔を近づけ、バーチャルボーイを顔に≪埋めた≫
ありま兄の顔の面積は、優にゴーグル部全体の面積を超えており、肥大化した顔の肉は吹き零れゴーグル全体の3分の1ほどを覆い込んだ。圧力でせりあがった部位のニキビが弾けて俺の顔に飛んだり、寄生虫が出てくるように、ニュルニュルとした脂が顔から排出され、ケーキのホイップのみたいにバーチャルボーイが飾られていった。
生まれて初めて、ゲームの手番が回ってこないで欲しいと思った。逃げ出そうにも、唯一の出入り口の引き戸の前をありま兄が背にする形で鎮座している。非常にわかりやすい形で、この怪物を倒さなければ家には帰れないことが示されていた。
「アアッ!!」ありま兄はコントローラーを雑に置き、ヌチャ…という水音とともにゆっくりと顔をあげた。その上半身は汗で濡れそぼって上気している。
「このハイスコア超えたらゲーム貸してやる。そしたら帰っていいからな」
俺はありま兄の粉瘤でマーキングされたバーチャルボーイの正面に座った。途端、涙が際限なく溢れてきた。
「ごめんなさい~!!!!!!許してください!!勝手に人の部屋に入るのは悪い事でした!!!もうしません!!!!もうゲームも借りなくて大丈夫です!!!!
二度とありま君とは遊びません!!帰らせてください!!!」
俺は、今までの人生の、本気で謝った経験を総動員して許しを乞うた。本屋で万引きしてしまったときも、お受験のために伸ばしていた妹の髪を勝手に切ってしまったときも、本気で謝れば大人は許してくれた。
「何言ってんの?だからゲームで勝ったら帰すっていう解決法だしたじゃん。俺、何か理不尽な事言ってる?」
「ごめんなさい、ゲームやりたくないです。ごめんなさい」
「それはダメだろ。それこそ理不尽だよ。場所には場所のルールがあんの。それを片方が一方的に破って、何の代償も払わずに日常に帰る事はできないの。しょうがないの。お前は俺の部屋にゲームを盗みにきてんだよ!!だから俺もお前をタダで帰すわけにはいかないの!!!世界の仕組みも知らねえガキが!!帰りてえならコントローラー握れ!!!」
今度は逃げるように、バーチャルボーイの世界へ潜った。おそらく一度も顔を上げなかったように思う。
「いいか!世の中にはな、どれだけ金持っていようが、どれだけ勉強ができようが、どれだけ容姿が優れていようがな、こうやって、ただゲームが弱いせいで死ぬこともあるんだよ!!!!」ゲーム画面の赤い視界の中で、ありま兄の言葉が耳を突き続けた。
どれくらいの時間ゲームしていたのかも分からないが、気づくと、俺は親の車に乗せられていた。ゲームに勝てたのかも覚えていない。ありま君、木下君、馬場君、佐藤の4人とは、この一件以来お互いに避け始め、話さなくなっていった。
18年経った、俺はあれからゲームを一切していない。TVをつけるとEスポーツプレイヤーの特集がやっていた。そこに写る、異様に濡れている人物、痩せていてもそれがありま兄だとはっきりと分かり、俺は思わず嘔吐した。そして思い出した。俺はあの日、嘔吐することによってゲームを中断させたのだ。
それから俺は、嘔吐することによって事態を切り抜ける術を、切り札のように胸に隠して生きている。